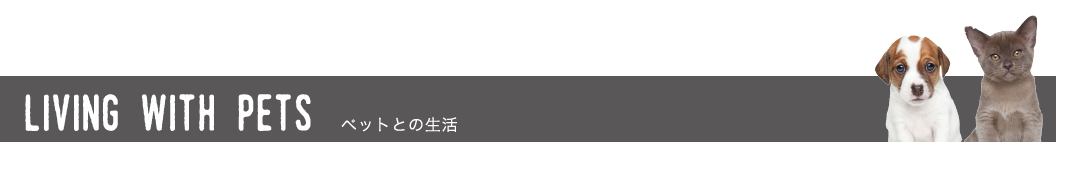

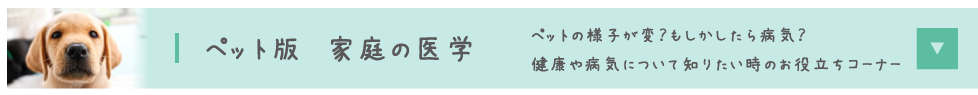
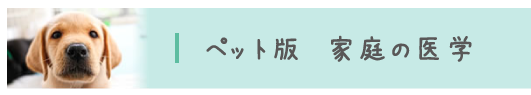
第23回 ペットに与えてはいけない人の食べ物


第22回 白内障について


第21回 夏の食中毒について


第20回 腎臓病について


第19回 “パテラ”ってなに? ~膝蓋骨脱臼について~


第18回 うちの子“でべそ”なんだけど…~臍ヘルニア、鼠径ヘルニアについて~


第17回 トゲを踏んでしまったときの対処法


第16回 ペット用救急箱を作ろう


第15回 シニア犬のケア


第14回 皮膚を痒がっているときの対応


第13回 トイレの状態をチェックしよう! ペットのおしっことうんちについて


第12回 おうちでのお薬の与え方


第11回 爪の切り方と深爪をしたときの対処法


第10回 ペットが溺れたときの対処法


第9回 どうして食べてくれないの? 食欲のない猫について


第8回 冬場に多い、ペットのやけど


第7回 垂れ耳の子は特に要注意!ワンちゃんの外耳炎について


第6回 歯みがきの重要性


第5回 心臓マッサージを知っておこう


第4回 電気コードをかじって失神! ペットの感電事故について


第3回 夏に気をつけたい ペットの熱中症について


第2回 何度も戻しちゃうんだけど、どうしよう?ペットの嘔吐について


第1回 何か変なもの食べちゃったかも! 愛犬の誤飲・誤食について




日本の夏は高温多湿で食べ物が傷みやすく、傷んだ食べ物を口にすることで食中毒が起こりやすいシーズンです。
暑さで傷んだ食べ物を口にすることでおこる”細菌性食中毒”は、人だけでなくペットにも起こりうる疾患です。
食中毒とは、体に悪いものを口にしたことによる病気全体を指す言葉で、ペットの場合、チョコレートや玉ねぎなど「人の食べ物でペットには毒となるもの」を食べたときの食中毒が最も多くみられます。しかし人と同じく、病原菌が付着した食べ物を口にすることによる細菌性食中毒も、夏の季節はペットにも多く発症します。「犬や猫は胃酸が強いので腐ったものを食べても大丈夫」と言われることもありますが、そんなことはありません。

食中毒を起こす細菌は10種類以上ありますが、多くは20度くらいで増殖し、動物の体温くらい(36度前後)で最も活発になります。どれも温度と水分があれば容易に増殖するので、食品に少量の菌が入っただけでもこの時期はあっという間に増えて食中毒の原因になります。
食中毒を起こす菌は大きく3つに分けることが出来ます
・感染型:細菌が食品内で一定数増殖し、それが消化管に感染して発症する。カンピロバクター、サルモネラ、 など
・生体内毒素型:細菌が消化管内で増殖する際に毒素を産生する。腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌(O157)、など
・毒素型:食品中で増殖しながら毒素を産生し、それを摂取することで発症する。黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌 など
これらの細菌は増殖しても、食品の見た目や味、匂いはさほど変わりません。また、食品内で作られた毒素は加熱して菌を死滅させても残ってしまいます。
主な症状は下痢と嘔吐です。繰り返すことによって脱水や血便などに進行してしまうこともあり、子犬子猫やシニアのペットは重症化しやすいので特に注意しなければなりません。
ペットがお腹を壊して食中毒かも、と思ったらすぐに動物病院に連れていきましょう。その時に、食べたものと吐いたもの、便などを一緒に持っていくと、原因の目安になります。
細菌性食中毒の治療は、軽症ならば抗生剤、整腸剤、下痢止め、吐き気止めなどを使って自宅療養になりますが、重症の場合は入院し、脱水を治すための点滴や、毒素を吸着する薬の投与などを行うこともあります。

最も大切なことは、食品に菌を付着させない、菌を増殖させる環境を作らないことです。
(菌を付着させない)
・食べ物に触る前には必ず手を洗いましょう。
・調理道具やフードボウルは常にきれいに洗って乾かしたものを使うようにしましょう。
・飲み水の容器にも注意が必要です。基本的に水は置いたままにしておくと思いますが、食事時間のたびに容器をよく洗って新しい水に替えましょう。ボトルタイプや流れるタイプの給水器を使用している場合も、同じくこまめに装置を洗い、水を入れ替えましょう。
(菌を増殖させない)
・食べないからと言ってフードを置きっぱなしにするのは良くありません。一定時間置いておいて、食べないようなら引き上げ、廃棄しましょう。
・ウェットフードは原則使い切り、開封した残りは必ず冷蔵庫に入れて1~2日で使い切るようにしましょう。
・ドライタイプのフードも酸化させたり湿気を吸わないように、開封したものはチャック付きポリ袋のような密閉容器に小分けにして、直射日光の当たらない涼しいところに保管しましょう。冷蔵庫はフードの表面が結露して却って湿っぽくなるため、お勧めしません。
・手作り食をする場合は、全ての食材を必ず加熱調理し、生肉や刺身などの生ものは避けるようにしましょう。
食中毒を起こす細菌はペットと人で同じものなので、人の食中毒がペットにも感染したり、飼い主とペットが同時に食中毒になることもあります。食中毒が疑われたらペットの食器やトイレだけでなく、台所の床や冷蔵庫や食器棚のドアなど、人の手が触ったところ、ペットが歩いたところなども消毒剤で拭いて除菌を徹底し、繰り返さないようにしましょう。
